国民健康保険 限度額適用認定証等の申請について
限度額適用認定証等の申請について
自己負担限度額を超える高額な医療費の支払いについて、医療機関窓口で「限度額認定証等」を提示することにより、あとから申請により、払い戻しを受けるのではなく、自己負担限度額までの支払いで済ませることができます。 医療費が高額になる場合は、事前に申請いただき、「限度額適用認定証等」の交付を受けてください。(申請した月の初日から有効となります。)
なお、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用すると、事前の手続なく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
70歳未満の人の場合
医療機関窓口で被保険者証とともに「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば、同じ医療機関で、入院・外来(調剤薬局を含む)ごとに自己負担限度額までの支払いで済みます。
また、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、入院時の1食あたりの食事代が減額されます。
いずれの所得区分も各認定証が必要となります。
70歳以上の人の場合
医療機関窓口で被保険者証と高齢受給者証を提示することにより、一般または現役並み所得者3の自己負担限度額までの負担となりますが、現役並み所得(1・2)の人は「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯(低所得1・2)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」も提示することで、さらにそれ以下の自己負担限度額までの支払いで済みます。
また、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、入院時の1食あたりの食事代が減額されます。
| 所得区分 | 判定基準 | 限度額認定証 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 住民税課税所得690万円以上の人及び同世帯の人 | 不要(注釈) |
| 現役並み所得者2 | 住民税課税所得380万円以上690万円未満の人及び同世帯の人 | 必要 |
| 現役並み所得者1 | 住民税課税所得145万円以上380万円未満の人及び同世帯の人 | 必要 |
| 一般 | 現役並み所得者、低所得者いずれにも該当しない人 | 不要(注釈) |
| 低所得者2 | 低所得1に該当しない住民税非課税の人 | 必要 |
| 低所得者1 | 世帯全員の所得が0円(年金収入80万円以下)となる住民税非課税世帯の人 | 必要 |
(注釈)現役並み所得者3、一般の人については、高齢受給者証を提示いただくと限度額が適用されます。
手続きに必要なもの
- 資格確認書等
- 申請者(世帯主)の「個人番号カード」または「個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)」




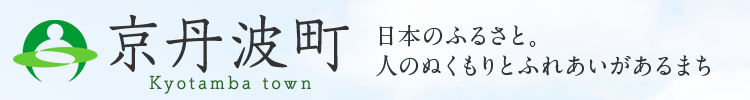
更新日:2022年12月01日